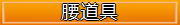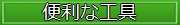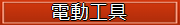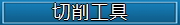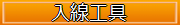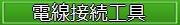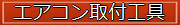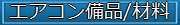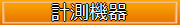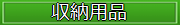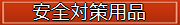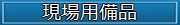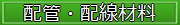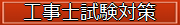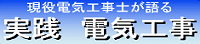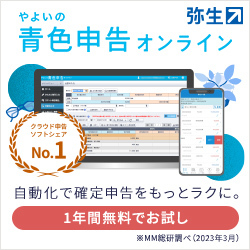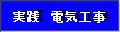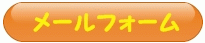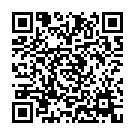墨つぼとチョークライン
墨だしには欠かせない 墨つぼとチョークライン
電気工事だけでなく建築工事では、いろんなところで墨だしをしています。
建築現場では基準となる墨から、間仕切り壁や天井高さ、土間の仕上がり高さなど、さまざまな仕上がり寸法を導き出します。
大工なら間仕切壁の位置やフロアの高さ、天上高など、左官屋や土工は、土間の仕上がり高や敷地のレベルなど、いろんな高さや位置を出さなくてはなりません。
私たち電気工事士も照明器具の取付位置やコンセント、スイッチ、分電盤、配電盤、キューピクル、電気室内のトランスや高圧盤の配置など、さまざまな機器の取付位置や高さなどを計測しなくてはなりません。
そのために、レーザー墨だし器を使って図面上に記された、いろんな指示に従って取付位置を正確に罫書き取付けていきますが、より確実に取りつけるために仕上げ前に墨だしを行い、直線などの墨打ち作業を行います。
電気工事の現場で作業してるのなら、この墨打ちをしてると思うけど、そのときに必要なのが墨つぼです。
一般的に、仕上げ材やコンクリート、モルタルなどで隠れるところでは、通常の墨つぼを使うと思うけど、墨つぼを使うと打った墨が消えないという利点があります。
しかし逆に考えれば、仕上げ材などに使うと、打った墨が消えないので仕上げ材を台無しにしてしまうということになってしまいます。
これでは、ほかの業者にも迷惑を掛けるし、手直しの費用負担も発生してしまいます。
そんなときは、チョークラインが便利です。
中身はチョークの粉なので、墨つぼのように一度付けると消えないということがないので、仕上がった土間や塗装が完了した、外壁でも使うことができるので
露出配管の墨だしのときなんかにもおすすめです。
また、屋内でも拭き取り可能な素材であれば、墨打ちできるから作業の効率も良くなります。
簡単だけど重要な墨だしにも、その使用目的に応じて使い分けることが求められるので、電気工事をするのであれば両方を持っておくことが大事でしょう。
もちろん、私も使用目的や使用場所によって、使い分けています。
墨つぼやチョークラインにもいろんなものがあるので、いくつか紹介しておくので、参考にしてください。
私が使ってる墨つぼとチョークライン
 |
タジマ(tajima) パーフェクト墨つぼ M PS-EVO-MBK
墨ダレが少なく、仕上げ材に飛ぶことも少なくて自動巻きも10mとほかのものに比べ長いので使いやすいんです。 |
|---|---|
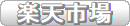 |
|
 |
タジマ(tajima) ピーラインチョークはや巻 PL-V3
墨打ちした時にチョークのカスレがないので、後の作業がスムーズになります。 |
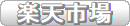 |
私は、どっちもタジマを使っています。
建築関連のいろいろな工具を販売している、建築関連の専門メーカーだから、現場で使いやすいものが多いからね。
墨汁とチョーク
 |
 |
|
墨運堂 |
シンワ測定 |
|---|---|
墨汁とチョーク粉だけど、どっちも別のものでもいいし、色もこだわる必要はないので、墨汁も朱色を使ってほかの墨と差別化するのもいいだろうし、チョーク粉も仕上げの色に近いものを使ったりして、少しでも早く消えるようなものを選ぶのも一つの考えです。
どちらも基本は見やすいことなので、そのあたりの整合性を考えて、使う色を決めるようにしてください。
タジマ(tajima)
墨つぼ
 |
 |
 |
|
タジマ |
タジマ |
タジマ |
|---|---|---|
チョークライン
 |
 |
 |
|
タジマ |
シンワ測定 |
たくみ |
|---|---|---|
いくつか墨つぼとチョークラインを紹介したけど、どれも用途は同じなので、気に入ったものを選べばいいです。
墨つぼを使っての墨打ちのときは、保護メガネの使うようにしてください。
カルコを使っての作業や二人で墨打ちをしてるときに、カルコが外れたり相手が放したときに、自動巻取り機能が働いてカルコが飛んで来ることがあり、目に刺さるると失明する可能性だってあるからね。
でも、保護メガネを一々使うのは面倒だから、そんな時は、スライド面付きヘルメットが便利ですよ^^
墨だしだけでなく、ハンガーレールのように金属切断の時でも簡単に使えるので煩わしい保護メガネの着脱をしなくてもいいからね^^
墨だしの方法についてはこちらをご覧ください。